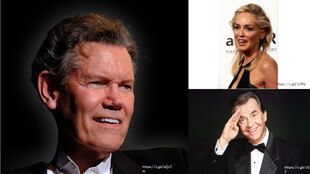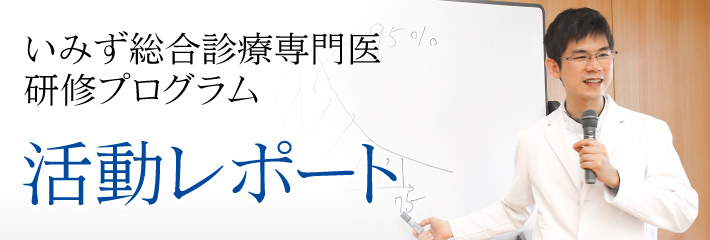
2025年10月3日(金)
講義受講報告【Communications Primer for the Public Health Sciences】
2024年3月からオンライン留学をしているJohns Hopkins大学にて、
2025-2026年度 第1タームに開講された
「公衆衛生科学のためのコミュニケーション入門」という講義を受講しました。
講義の内容は、効果的な口頭・文章での表現を演習形式で学び、明確さと簡潔さを大切にしながら、「核心的なメッセージ」を届ける方法を身につけるというものでした。
◎講義の学び:映画と舞台からの発想
講義の中で強調されたのは「教育 = 物語」という考え方でした。
何かを伝える時、あるいは教える時、それは単に情報を伝えるのではなく、物語性(Narrative)を持たせることで、聞いておられる方の理解・記憶・意欲に大きく影響するという理論です。
対立(Conflict)
キャラクター(Character)
ペース(Pace)
これらを組み込み、プレゼンを複数幕の舞台や映画のように構成すると、聞いておられる方は「理解の旅」を体験することができると学びました。
また「アウトラインスライドは不要」というアドバイスも新鮮でした。
代わりに 問いかけや大胆な主張からスタートし、最後は一番伝えたいメッセージで締めくくる。
この構成が、短時間のプレゼンテーションに非常に有効であると知りました。
◎実践:私が作成したプレゼン資料
今回の課題で取り組んだテーマは、脳卒中と内臓脂肪(Visceral Fat)の関係です。
アメリカでは約300万人の脳卒中サバイバーが、家族や友人などの「非公式介護者」に支えられていること。内臓脂肪は虚血性脳卒中の主要なリスク因子であることを示す疫学データ。
忙しい人でもできる、効率的で時間のかからないレジスタンストレーニングの紹介。
こうした流れを「問題 → 解決策 → 行動喚起(Action)」の物語構造に沿って組み立てました。
実際にスライドを並べてみると、「PowerPointはカメラ」という比喩の意味が腑に落ちました。
情報をすべて盛り込むのではなく、「今この瞬間に見せたい一枚」を切り取ることが、聞いておられる方にメッセージを残す鍵になるのだと実感しました。
◎まとめ
本講義を通じて、プレゼンテーションは単なる情報伝達ではなく、人を動かすためのストーリーテリングであることを学びました。特に、公衆衛生という分野は誰もが関わり得る領域です。だからこそ、誰にでも伝わる言葉で、心に届く構成を意識することが重要だと感じます。
また、医師として症例報告はもちろんプレゼンテーションの機会をいただくことも多いので、実践を繰り返し、表現力を磨いていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
2025-2026年度 第1タームに開講された
「公衆衛生科学のためのコミュニケーション入門」という講義を受講しました。
講義の内容は、効果的な口頭・文章での表現を演習形式で学び、明確さと簡潔さを大切にしながら、「核心的なメッセージ」を届ける方法を身につけるというものでした。
◎講義の学び:映画と舞台からの発想
講義の中で強調されたのは「教育 = 物語」という考え方でした。
何かを伝える時、あるいは教える時、それは単に情報を伝えるのではなく、物語性(Narrative)を持たせることで、聞いておられる方の理解・記憶・意欲に大きく影響するという理論です。
対立(Conflict)
キャラクター(Character)
ペース(Pace)
これらを組み込み、プレゼンを複数幕の舞台や映画のように構成すると、聞いておられる方は「理解の旅」を体験することができると学びました。
また「アウトラインスライドは不要」というアドバイスも新鮮でした。
代わりに 問いかけや大胆な主張からスタートし、最後は一番伝えたいメッセージで締めくくる。
この構成が、短時間のプレゼンテーションに非常に有効であると知りました。
◎実践:私が作成したプレゼン資料
今回の課題で取り組んだテーマは、脳卒中と内臓脂肪(Visceral Fat)の関係です。
アメリカでは約300万人の脳卒中サバイバーが、家族や友人などの「非公式介護者」に支えられていること。内臓脂肪は虚血性脳卒中の主要なリスク因子であることを示す疫学データ。
忙しい人でもできる、効率的で時間のかからないレジスタンストレーニングの紹介。
こうした流れを「問題 → 解決策 → 行動喚起(Action)」の物語構造に沿って組み立てました。
実際にスライドを並べてみると、「PowerPointはカメラ」という比喩の意味が腑に落ちました。
情報をすべて盛り込むのではなく、「今この瞬間に見せたい一枚」を切り取ることが、聞いておられる方にメッセージを残す鍵になるのだと実感しました。
◎まとめ
本講義を通じて、プレゼンテーションは単なる情報伝達ではなく、人を動かすためのストーリーテリングであることを学びました。特に、公衆衛生という分野は誰もが関わり得る領域です。だからこそ、誰にでも伝わる言葉で、心に届く構成を意識することが重要だと感じます。
また、医師として症例報告はもちろんプレゼンテーションの機会をいただくことも多いので、実践を繰り返し、表現力を磨いていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。