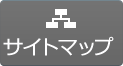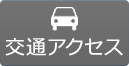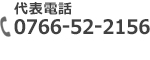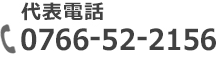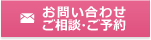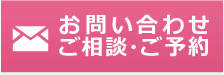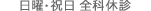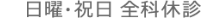病む人を理解する
私たちが医療者として成長するために大切なことをウイリアム・
オスラー博士の言葉で紹介します。
「患者がどんな病気にかかっているかよりも、その病気に
かかっている患者がどんな人かを知る方がはるかに大切である。」
同じ病名の付く患者さんでも、苦しみ方、悩み方、病み方は千差万別、
その人ごとに治療を変えなければならないことがよくあります。応病
与薬の”病”を病気ではなく、”病人”として捉え、その人にあった関わり
をして行かねばならず、対応の難しさをいつも知らされます。
人ごとに違う部分が多い中、共通点もあります。
・甲乙付け難い
病は丙という字が疒(ヤマイダレ)の中に入っています。
どんな病気も、それを患っている人にとってはとても辛く、この
病気だからまだマシだと本人の立場ではなかなか思えません。
だから病は甲乙つけがたく「丙」という字があてられているそう
です。辛い思いが強いほど、わかって欲しいという心は大きくなり
ますので、その心に沿った対応が必要になります。
・病が人を変える
病の苦しみや不安がその人の人格や風貌まで変えてしまうことが
あります。そこまで思いが至らず、そんな人だと決めつけては失敗
します。病気がこの人をそうさせているのだなと思うことが、その
人を理解する一歩になると思います。
日々、反省の連続ですが、患者さんが笑顔になられたかどうかを自分
の対応の良し悪しの目安にし、笑顔の溢れる素晴らしい医療を行い
ましょう。